「理屈ではわかっていたのに、気づけば間違った判断をしていた…」
投資やお金の管理でこんな経験はありませんか?
私たちは合理的に行動しているつもりでも、感情や思考のクセ=“心理バイアス”に知らず知らずのうちに影響されています。
この記事では、代表的な心理バイアスとその具体例、克服のためのヒントをわかりやすく紹介します。
感情とうまく付き合いながら、大切な資産を守るための一歩を踏み出しましょう。
心理的バイアスが意思決定を狂わせる理由
そもそも人間の脳は「損失を強く恐れる」ようにできています。
たとえ合理的に考えたつもりでも、感情が判断に大きく影響します。
また、私たちは目先の快楽や安心感を求めがちです。
こうした性質が、長期的に見れば損になる行動を選ばせることもあります。
代表的な5つの心理バイアス
以下の5つは特にお金に関する意思決定でよく表れます。
① サンクコスト効果
「ここまでお金を突っ込んだから、やめられない…」
こんな気持ちになったことはありませんか?
下がり続ける株を「いつか上がる」と信じてナンピン(買い増し)し、結局塩漬けにして放置する。
これが典型的なサンクコスト効果です。
② 確証バイアス
「自分の意見を支持する情報だけ集める」
以前、ホログラフィックAR(拡張現実)を使った広告技術を提供する企業に投資したとき、株価がどんどん下がっていました。
それでも「世間が気づいていないだけ。もう少ししたら高騰する」と、都合のいい情報ばかり集めていました。
結果は惨敗でしたが、今となっては大事な学びです。
③ 損失回避性
「少しの下落で売ってしまう」
損を避けたい気持ちが強く、不安のある株をほんの少し下がっただけで手放してしまうことがあります。
長期で上がる見込みがあるのに、短期の値動きに振り回される典型例です。
④ 現状維持バイアス
「変えるより今のままが安心」
スマホの通信会社や保険の見直しが面倒で、つい同じものを使い続けてしまう。
私も通信会社を乗り換えるときはかなり腰が重かったですが、実際に変えたら通信費がぐっと下がりました。
手間に感じることでも、一歩踏み出すと結果が変わります。
⑤ アンカリング効果
「最初に見た数字に引っ張られる」
たとえば、株価の過去最高値を基準に「まだ安いから買いだ」と判断する。
根拠のない基準に縛られてしまうのがアンカリングです。
心理バイアスを克服するための具体策
心理バイアスを完全に消すことはできませんが、次の工夫で影響を減らせます。
- 判断基準をルール化する
「この条件を満たしたら売る・買う」と事前に決めることで、感情に振り回されにくくなります。 - 他人に相談して客観性を確保する
信頼できる人に意見をもらうだけで、視野が広がります。 - 小さな意思決定の練習を積む
身近なお金の選択で「ルールに従う練習」をすることで、大きな判断でも冷静になれます。
人と話したりして自分の視野が狭くなっていないかを確認することが大切です。
感情と上手に付き合いながら資産を守る
感情を完全に排除するのは不可能です。
大事なのは「自分はこういうバイアスに弱い」と知ったうえで、対策を講じること。
バイアスを理解し、行動の癖を少しずつ改善するだけでも、投資やお金の管理が大きく変わります。
まとめ
知識だけではなく、自分の思考のクセに気づくことが行動改善の第一歩です。
心理バイアスを意識するだけで、無駄遣いや投資の失敗を減らせます。
「知っているだけで変わることがある」
今日から少しずつ試してみてください。

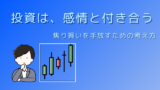


コメント