「ネタが思いつかない」「書こうとしても薄く感じる」──そんな悩み、ありませんか?
私も以前、同じように悩んでいました。でもある日、ふと気づいたんです。
うまく書けない理由は、「書く力」ではなく「見る力」が足りなかったのかもしれない、と。
通勤中の風景、何気ない会話、読んだ本の一文。
特別な出来事がなくても、日常を観察することで、文章に深みや共感が生まれるようになりました。
今回はそんな体験をもとに、“観察する力”が文章を変えるという話をお届けします。
観察力があると、文章は変わる
「観察」というと、“よく見る”ことだと思われがちですが、
本質は「よく感じる」ことだと、私は思います。
たとえば、ただ「ラーメン屋が混んでいた」と書くよりも、
「小雨が降る平日。にもかかわらず、15人が傘をさして並ぶ。店の外からは、にんにくの香りがはっきり届いていた。」
と描写すれば、読者の中に情景が浮かびます。
こうした“本人にしか知りえない情報”が、文章にリアリティを生み出します。
これは技術というより、
「見ているものを、どれだけ丁寧に受け止めているか」の違い。
そしてその力は、日々の中で確実に鍛えることができるのです。
通勤中も、ヒントの宝庫
朝の電車。私はよく、人を“観察”しています。
- スマホを食い入るように見ている人
- ぼーっと車窓を見つめる人
- 本や参考書を読んでいる学生
「この人、今どんな気分なんだろう?」
「何を見ているんだろう?ニュース?ゲーム?」
「試験が近いのかも…」
こうした想像は、文章を書くときの“背景描写”として活きてきます。
読者に「朝の通勤がつらい人」が多ければ、
実際の空気感を思い出して、冒頭の一文にリアリティを込めることもできます。
会話の中にも“ヒント”がある
ふとした雑談も、観察の場です。
たとえば同僚がこう言ったとします。
「最近、休みの日でも疲れが取れないんだよね…」
これを「そうなんだ〜」で終わらせるか、「なぜそう感じているんだろう?」と掘り下げるかで、得られる情報は変わってきます。
- 家事がたまっているのかも?
- 夜ふかししてるのかも?
- 通勤がストレスになっている?
こうした“背景”を言語化できると、読者が「これ、自分のことだ」と感じてくれる文章につながります。
そして、言葉以上に確かなのが「行動」からの読み取りです。
行動には、本人が“せざるを得ない理由”や“どうしてもやりたい気持ち”が表れます。
その背景に目を向けることで、発想がより深く、広がっていくのです。
読書は観察力のトレーニングになる
読書もまた、観察の力を養う絶好の機会です。
特におすすめなのは、登場人物の“内面”を想像しながら読むこと。
たとえば、登場人物が怒っている場面。
「怒っている」と書かれていたら、それだけで終わらせず、
- なぜ怒っているのか?
- どういう価値観の人なのか?
- 背景にどんな出来事があったのか?
と、自分なりに深掘りしてみる。
この習慣が身につくと、他人の気持ちを“文章で再現する力”がぐっと強くなります。
人が抱えるモヤモヤや葛藤を、言葉にして表現できるようになる。
それは、読者の「気持ちに寄り添える文章」につながるのです。
もちろん、深掘りの答えが正解とは限りません。
でも大切なのは、“自分以外の誰か”に思いを馳せてみること。
答えが違っていたとしても、「そんな視点もあるのか」と受け止めること。
それが、伝える文章の“懐の深さ”につながります。
まとめ:「観察眼」は、文章の土台になる
「特別なネタがないから、いい文章が書けない」
そう思ってしまうこと、私にもあります。
でも、実は“観察する力”があれば、どんな日常も「伝える文章」のタネになります。
- 通勤中のふとした気づき
- 会話の中にあるリアルな声
- 読書から得た他人の視点
こうした小さな積み重ねが、やがて読者に「共感される文章」になっていくのです。
あとがき
私は文章を書くとき、なるべく「自分の目の前にある現実」からヒントを探すようにしています。
観察することは、書くことと同じくらい大切。
そして、それは特別な人だけが持っている力ではありません。
黒川あかねのように──
徹底的に相手を見て、感じて、なりきる。
そんな“観察の姿勢”を、私たちも日常の中で育てていけたら、
もっと深く、もっと伝わる文章が書けるようになるのではないでしょうか。
それでは
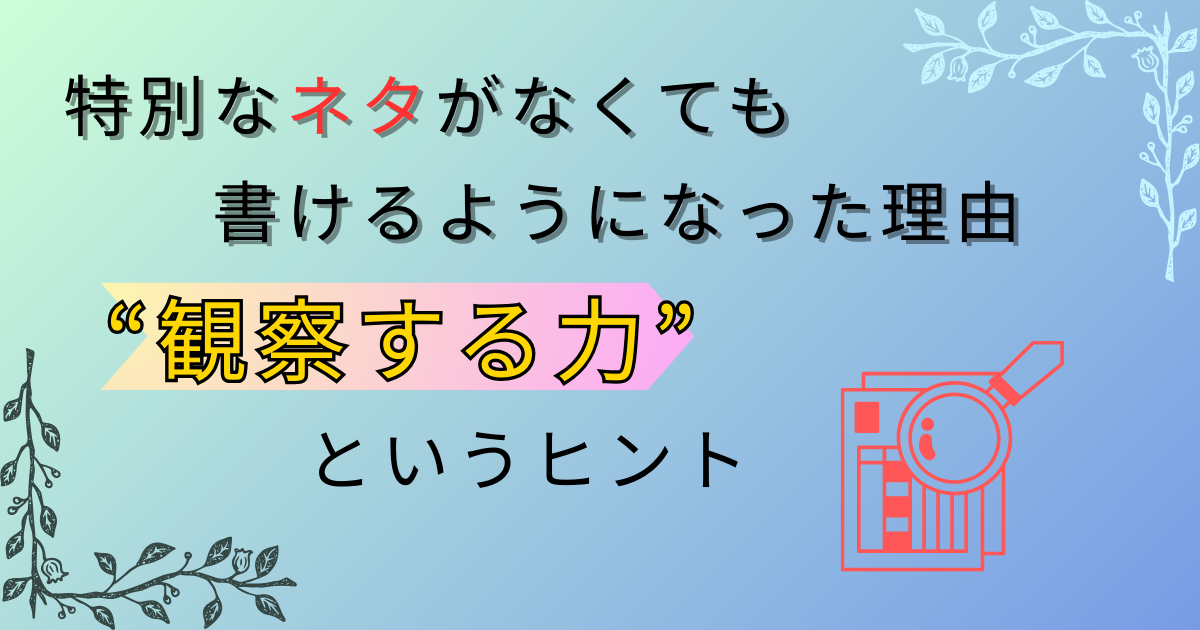

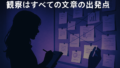

コメント